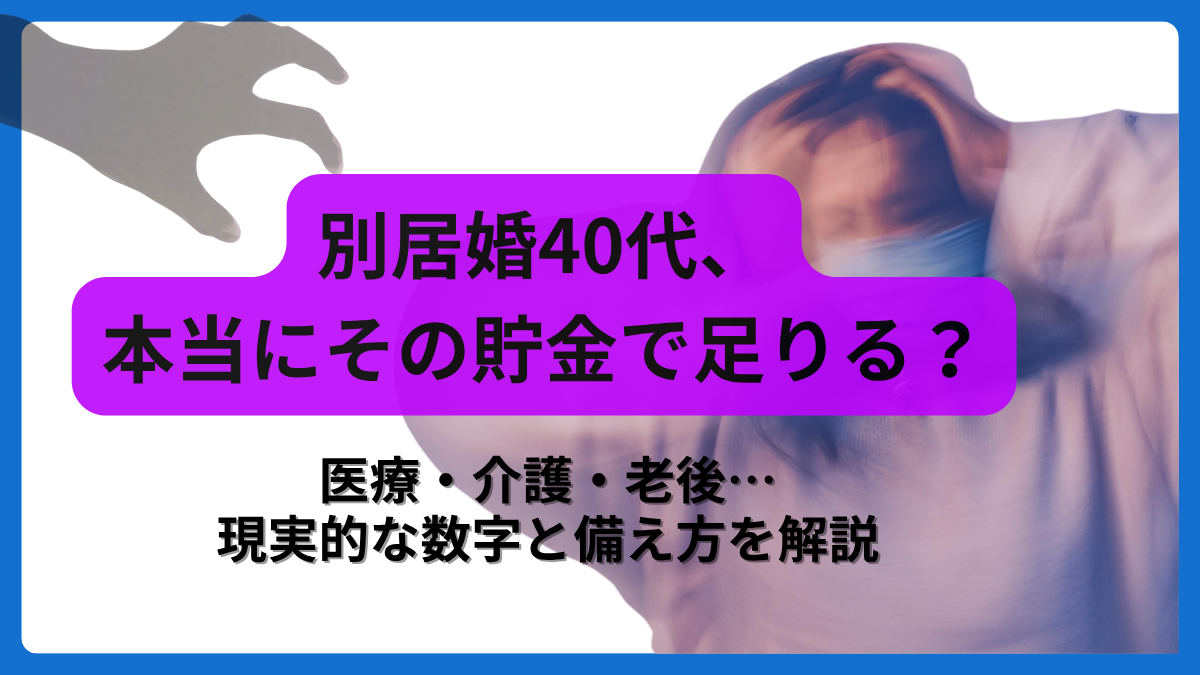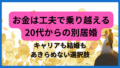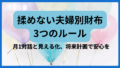40代別居婚の貯金術│老後資金・お金の管理法を解説
40代になると、仕事や収入が安定してきて、将来のライフイベント(出産・育児・老後資金など)を現実的に考える時期に入ります。
しかし「別居婚」というライフスタイルを選んでいる場合、生活費や貯金、年金といったお金のテーマがより複雑に感じられることもあります。住居費や交通費が二重にかかりやすく、同居夫婦とは違う工夫が求められるからです。
この記事では、40代の別居婚における家計管理のリアルを解説します。生活費や貯蓄の考え方、老後資金への備えまで、筆者の体験と公的データを交えて紹介。将来の安心を得るために、今日から取り入れられるヒントをお届けします。
🔍 この記事でわかること
- 40代別居婚に必要な生活費と貯金の目安
- 年金・老後資金を見据えた家計管理の工夫
- 実際に役立つ制度や節約ポイント
💡別居婚にかかるお金の全体像を知りたい方は、こちらも参考にどうぞ:
別居婚のお金のリアル:必要な年収と生活費を徹底解説
40代別居婚にかかる生活費と貯金計画の現実

住居費・光熱費・通信費|単身生活の基本コスト
別居婚では、原則として夫婦それぞれが別々の住居を持つため、住居費や光熱費が二重にかかる点が最大の特徴です。
では実際に、どれくらいの支出になるのでしょうか。
総務省「家計調査(単身世帯・勤労者世帯)2023年」によると、1人暮らしにおける月々の平均支出は以下の通りです:
| 項目 | 平均支出(月) |
|---|---|
| 住居費 | 約15,000円(※賃貸の場合、家賃補助含む) |
| 光熱・水道 | 約12,000円 |
| 通信費 | 約8,000円 |
ただし、都市部で賃貸物件に暮らす場合、住居費は月7〜12万円が現実的な目安になります。
夫婦それぞれがこの額を負担すると、月14〜24万円の住居関連コストが発生することになります。
また、光熱費・通信費なども各家庭で発生するため、「結婚してもコストは2倍近くかかる」と感じる人も少なくありません。
食費・日用品費・交際費|意外に見落としがちな支出
| 項目 | 平均支出(月) |
|---|---|
| 食費(単身) | 約30,000~50,000円 |
| 日用品費 | 約5,000~8,000円 |
| 交際費 | 週末の外食や宿泊費などで月1〜2万円ほど |
「別居しているからこそ、週末は外食で贅沢したい」「どちらかが移動してホテル泊になる」など、生活コストだけでなく“会うための費用”も発生する点に注意が必要です。
さらに言えば、この出費は毎月の固定費にプラスされるため、家計全体のバランスを考えるうえで重要な要素となります。
交通費・子ども関連費用がある場合の注意点
- 月2回の新幹線往復:1〜3万円 × 2回 = 月2〜6万円
- 高速道路+ガソリン代:月1〜2万円
また、子どもがいる家庭では教育費・保育費・医療費も発生するため、別居婚のまま子育てをする場合はさらに支出が膨らむ可能性があります。
交通費の節約についてはこちらに詳しく解説しました:
👉 遠距離恋愛・別居婚の交通費の工夫集
老後資金と年金を見据えた40代の家計管理
生活防衛費+ライフイベント備え=最低〇万円が目安
40代で別居婚を続けるには、日々の生活費に加えて、予期せぬトラブルにも対応できる「生活防衛費」を準備しておくことが重要です。
一般的に、生活防衛費は「生活費の6か月分」が目安とされています(金融広報中央委員会『知るぽると』より)。
たとえば、以下のような支出の場合:
-
月々の生活費(住居費+食費+交通費など):約20万円
⇒ 生活防衛費:20万円 × 6か月 = 120万円
※ここで紹介している生活防衛費(120万円)は、別居婚における「片方の生活費」を想定した目安です。
夫婦でそれぞれの生活を維持している場合は、パートナーの分も含めて、家計全体の視点で必要額を見積もっていくと安心です。
より安心して暮らすためには、生活防衛費に加え、医療・介護・設備更新に備えた資金が必要です。
医療費・介護費など老後資金のシミュレーション
医療や介護に関する支出は、発生する時期や金額の予測が難しいため、生活費とは別に「ゆとり資金」として準備しておくことが推奨されます。
ゆとり資金の内訳(目安)
| 項目 | 概算 |
|---|---|
| 医療費一時負担 | 20〜40万円 |
| 介護初期費用+1年分自己負担 | 100〜150万円 |
| 設備・家電の更新 | 10〜30万円 |
| 合計(目安) | 130〜220万円 |
参考:生命保険文化センター|介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?
医療費の備え
-
高額療養費制度を使っても、月8〜9万円までは一時的に自己負担が必要
-
入院時の食事代・差額ベッド代・自由診療など、制度外の費用もある
-
→ 1〜2か月の入院に備え、20〜40万円程度の現金を確保
介護費用の備え
-
生命保険文化センターの調査によると、介護にかかる総額平均は約500万円
-
初期費用(施設入所、住宅改修)や1年分の自己負担額として、100〜150万円程度を想定
家電やインフラの更新費用
-
単身生活では家電・家具・設備の更新もすべて自己負担
-
→ 年間10〜30万円ほどの突発支出が起こりうる
これらを踏まえると、ゆとり資金として130〜220万円程度を確保しておくと安心です。
40代別居婚の貯金目安(最低ライン)
生活防衛費に加え、医療・介護・設備更新に備えたゆとり資金が必要です。40代別居婚の夫婦であれば、250万円以上の貯金があれば想定外のトラブルにも対処できるでしょう。
| 項目 | 最低額 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活防衛費 | 120万円 | 生活費・医療費など |
| ゆとり資金 | 130〜220万円 | 家電買い替え、旅行・帰省 |
| 合計 | 250〜340万円 | 突発支出に備えた貯金 |
※片方(夫または妻)の分です。別居婚ではそれぞれが準備する前提で考えましょう。
年金と貯金のバランス設計──別居婚40代が今できること

最初に、日本年金機構の「ねんきんネット」で年金見込み額を確認しましょう。
老後に向けた資金準備で欠かせないのが「年金の見える化」です。
まずは、日本年金機構の『ねんきんネット』を使って、自分が将来受け取れる年金見込額を確認しましょう。
【参考リンク】
👉 ねんきんネット|日本年金機構
例:将来の年金額が月13万円だった場合
-
単身生活の最低支出:月15〜18万円
⇒ 年金だけでは足りない可能性が高いため、不足分(2〜5万円)を補える資産形成が必要になります。
40代別居婚夫婦が貯金を確保するために、今からできること
40代からの貯金づくりには、日々の家計管理だけでなく、制度の活用や仕組みづくりがカギになります。ここでは、無理なく続けられる資産形成や管理の工夫を紹介します。
別居婚での節約についてはこちらにまとめています:
👉 別居婚でできる節約工夫まとめ
iDeCoやつみたてNISAを活用して、資産をじっくり育てる
税制優遇を活かした制度で、長期的に老後資金を積み立てるのが基本です。
特にiDeCoは老後資金専用として貯められるため、「確保した貯金には手を付けない」意識づけにもなります。
家計の「三分割」で、目的別に管理する
支出・予備費・将来資金をひとつの口座で管理していると、
「本当に備えられているのか?」が見えにくくなります。そこで筆者がおすすめしたいのが“目的別口座”の活用です。
-
日々の生活費用(家賃・食費など)
-
緊急出費用(医療費、家電の買い替え)
-
長期貯金・老後資金(つみたてNISAや定期預金)
分けておくことで、「何のためのお金なのか」が明確になり、不安の正体も整理しやすくなります。
年1回、家計の“棚卸しタイム”をつくる
毎月の家計管理が苦手な人でも、年1回の見直し日を設定しておけばOKです。
たとえば結婚記念日や年末年始など、家族の節目にこんなことを見直しましょう。
-
固定費(家賃、通信、サブスクなど)の見直し
-
年金見込み額やiDeCo・NISAの積立状況の確認
-
パートナーと将来の備え方・分担について共有
「定例イベント」にすることで、別居婚でも“同じ未来”を確認するきっかけになり、安心感にもつながります。
このように、今からできる小さな工夫の積み重ねが、40代以降の暮らしにとって大きな「安心の種」になります。
別財布管理のコツはこちら:
👉 夫婦別財布で喧嘩しないためのルール
別居婚40代こそ、自分らしいお金の仕組みを持とう
- 住居費や交通費など2拠点分の生活費がかかる
- 200〜300万円の貯金が安心ライン
- 医療・介護・家電の出費に備えるゆとり資金が必要
- 年金と貯金の差分を埋める資産形成を始め30
将来が不安に感じるときこそ、自分たちに合ったお金の仕組みを考えるチャンスです。
お互いのスタイルを尊重しながら、安心と自由を両立させていきましょう。
暮らし方の選択肢もチェック:
👉 別居婚のメリットとは?私たちのリアルな暮らし
👉 別居婚のデメリット│上手くいかない理由とは?