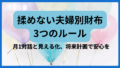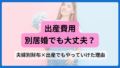別居婚で迎えた初めての出産|立ち会いなしでも夫婦の絆を深めた方法
初めての出産をひとりで迎え、別居婚のまま育児をしていくことに、不安がなかったわけではありません。でも、「距離があるからこそ生まれたつながり」や「思いやり」がありました。
立ち会えなかったけれど、私たちは一緒に出産を経験しました。そして、離れていても夫婦で子育てと向き合うことはできる──その実感があります。
別居婚という形はまだ少数派ですが、「どう一緒に歩むか」が何よりも大切。今、不安を感じている妊婦さんや、育児中の方にも、「こんな形でも大丈夫」と伝えたいです。
こちらもどうぞ 👉 0歳の子育てがしんどい…ワンオペで悩んだ私のリアルと今すぐできる対策
🔍 この記事でわかること
- 妊娠・出産を別居婚で迎えるリアルなプロセス
- 立ち会いができなくても夫婦の絆を深める方法
- 遠距離でも育児を協力しあう工夫と心の支え
📌 妊娠がわかった日と、別居婚での準備
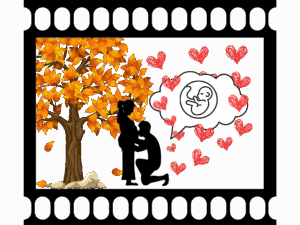
妊娠がわかった日、私は電話で夫に伝えました。画面越しの声は驚きと喜びにあふれていて、その瞬間は本当に嬉しかったことを覚えています。私たちは、いわゆる「別居婚」で、遠距離で暮らしており、会えるのは限られたタイミングでした。
私たちは、いわゆる「別居婚」で、遠距離で暮らしており、会えるのは限られたタイミングでした。
(👉 別居婚のスタイルについてはこちらの記事もどうぞ)
妊娠してからの健診はすべて一人で受けましたが、病院の待合室には旦那さんに付き添ってもらっている妊婦さんもたくさんいて、少しだけうらやましく感じることもありました。
でも、私は「私は一人でも大丈夫」と自分に言い聞かせていました。夫婦で別居で出産・育児に臨むと決めていたからです。エコーの画像や赤ちゃんの成長記録は、すぐに夫に送って報告しました。また、妊娠中は毎晩の夕食を写真で共有。妊娠前は食が細く心配されていたので、私なりに「ちゃんと食べてるよ」という安心を伝えたかったんです。
✨ 立ち会いなし出産を選んだ理由
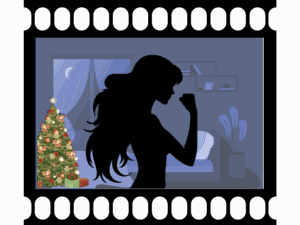
妊娠後期になると、周囲から「立ち会い出産するの?」「来てくれるの?」という言葉をよくかけられるようになりました。正直なところ、最初は私も「立ち会ってほしい」と思っていました。
でも現実的なハードルがありました。夫は仕事の都合で急に休みを取ることが難しく、出産のタイミングは予測不可能。「立ち会える保証」がなかったのです。また、私自身にも「そばにいてほしい」気持ちと「苦しんでいる姿を見られたくない」気持ちが入り混じっていました。
最終的に私たちは、ふたりで納得して「立ち会いなし」の出産を選びました。無理をせず、でも気持ちのつながりは保つ──そんな私たちらしい決断でした。
🍼 妊娠期間中に離れていてもできた工夫
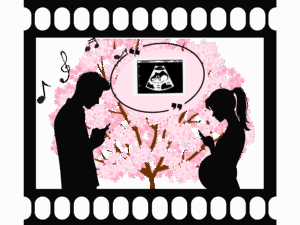
ひとりでの妊婦健診は、慣れるまではやっぱり少し心細かったです。特に、初めて心拍を確認したときや、性別が分かった日──あの瞬間を一緒に共有できたら、もっと特別に感じられたのかもしれません。
でも「一緒にいられない」からこそ、私たちは“共有する努力”を重ねました。健診内容はすべてメモして、エコー写真も毎回夫に送信。
※妊婦健診は、多くの自治体で公費助成を受けられます。
たとえば厚生労働省の調査によれば、妊婦1人あたり平均約10万円の助成が実施されています。
詳細は 厚生労働省|妊婦健康診査の公費負担の状況(全国調査) をご確認ください。
夕飯の写真も共有アプリで送り、「今日は病院で‘順調’って言ってもらえたよ」「このごはん、○○にもいいらしい!」とコメントを添えていました。
出産直前、夫に手紙を渡しました。「立ち会いはできないけれど、もう生まれるというときになったら読んでね」と伝えて。
産後クライシスの不安もあり、今のうちに感謝と愛情を伝えておきたかったのです。夫は手紙のことに触れませんでしたが、産後の私の変化には敏感に気づき、言葉少なに気遣ってくれました。手紙の想いが、きっと届いていたのだと思います。
また、妊娠中は夫が父親になる実感をなかなか持てないことに悩みました。私は母になる準備を進める中で、夫との温度差に寂しさを感じることも。そんなときは夜に電話をし、「もっと赤ちゃんや私のことを考えてほしい」と正直に伝えました。夫は謝るだけでなく「どうすれば協力できるか」を一緒に考えてくれました。
🔸 出産当日の出来事と心の支え
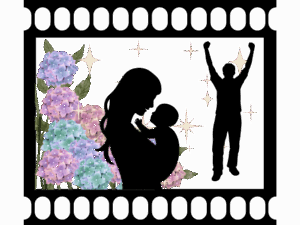
その日は突然やってきました。朝、お腹に違和感があり病院に連絡すると「すぐ来てください」と。タクシーで病院へ向かい、ひとりで診察室へ入りました。
夫は仕事中で電話に出られず、着信履歴だけが残る中、不安と緊張が募りました。しばらくして夫からかかってきた電話を繋いだまま、私は陣痛と闘いました。声を聞くだけで、本当に安心できました。
陣痛は24時間以上にわたり、最後は緊急帝王切開へ。母が駆けつけてくれて、手術の同意書にサインをしてくれました。そして赤ちゃんと対面した瞬間、「この子が本当に私の中にいたんだ」と、すべての苦しみが報われる思いでした。
❤️ 別居婚で育児をするという選択
出産後、退院の日には夫が迎えに来てくれ、数日間は3人で過ごせました。赤ちゃんを抱く夫を見て、「この人と家族になれてよかった」と心から思いました。
その後はまたそれぞれの場所で生活を続けています。もちろん「一緒に住んでいたらもっと楽かも」と思う瞬間もあります。
👉 別居婚での0歳育児のリアルや、ワンオペの乗り越え方はこちらで詳しくまとめています:
0歳の子育てがしんどい…ワンオペで悩んだ私のリアルと今すぐできる対策
一方で、同居による育児ストレスの話もよく耳にします。
我が家では、夫が来たときには育児に積極的に関わってくれます。私のやり方と違っても、口出しはせず、夫の姿勢を尊重しています。別居婚だからこそ、お互いの育児への向き合い方を認め合える──そんな関係に、私は安心と希望を感じています。
💡 別居婚でも立ち会いがなくても心はひとつ
- 別居婚でも妊娠・出産を安心して迎えることはできる
- 立ち会いがなくても、気持ちのつながりは育める
- 離れていても、育児に向き合うことは可能
- 夫婦で思いやりや共有の工夫を重ねることが大切
初めての出産をひとりで迎え、別居婚のまま育児をしていくことに、不安がなかったわけではありません。でも、「距離があるからこそ生まれたつながり」や「思いやり」がありました。
立ち会えなかったけれど、私たちは一緒に出産を経験しました。そして、離れていても夫婦で子育てと向き合うことはできる──その実感があります。
別居婚という形はまだ少数派ですが、「どう一緒に歩むか」が何よりも大切。今、不安を感じている妊婦さんや、育児中の方にも、「こんな形でも大丈夫」と伝えたいです。