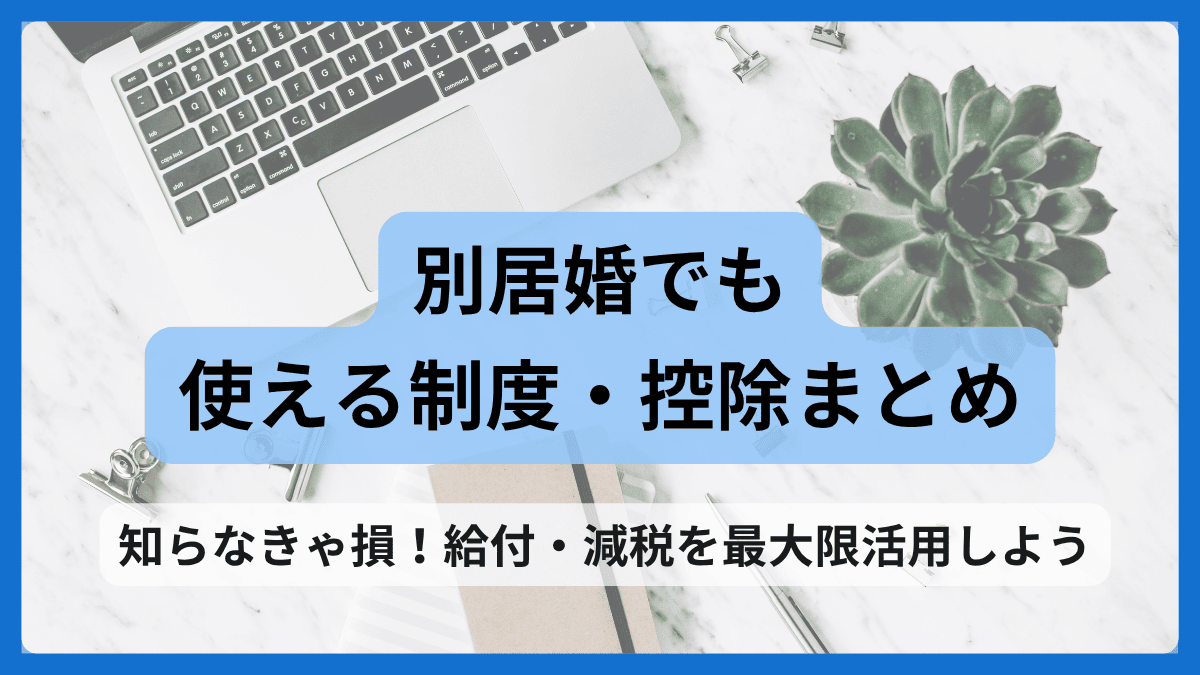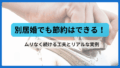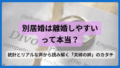別居婚で使える制度・控除まとめ|給付・減税ガイド
「別居婚って、同居してないから制度の対象外になりそう…」
そんな不安から、医療費控除や扶養控除、育児手当や給付金などを“使えないもの”と思い込んでいる方も少なくありません。
ですが実際には、条件を満たせば別居婚でも多くの制度を活用できます。筆者自身も、出産時に医療費控除や育児給付を受けた経験があります。
この記事では、別居婚でも損せず使える制度・控除を、減税編・給付編に分けてわかりやすく解説。
「どうすれば使えるのか?」「申請のポイントは?」など、行動に直結する情報をまとめています。
正しい知識を持てば、別居婚でも制度の恩恵を受けて、安心して暮らすことができます。
🔍 この記事でわかること
- 別居婚でも使える控除・給付制度の種類
- それぞれの制度の条件と注意点
- 申請時に損をしないためのチェックポイント
別居婚でも制度は使える?基本の考え方

「制度って、同居していることが前提なのでは?」
そう感じる方も多いかもしれません。
でも実は、多くの公的制度や控除は、実態として“生計を一にしているかどうか”を基準に判断されます。
つまり、住民票の住所が別でも、送金・扶養・育児などの実態があれば対象になることもあるのです。
制度の対象は「同居」前提じゃない
たとえば国税庁の「扶養控除」に関する説明では、“住所が異なっていても、生活費や療養費などを負担していれば扶養に該当する可能性がある”と明記されています。
これは医療費控除や育児給付など、ほかの制度にも共通する考え方です。
条件次第で別居でも対象になることが多い
別居婚だからといって制度をあきらめる必要はありません。
ただし、条件を満たしているかどうかを正確に確認し、必要書類や証明を準備しておくことが大切です。
自治体や職場によって運用ルールが異なる場合もあるため、「別居=対象外」と決めつけず、まずは確認してみましょう。
私たちも医療費控除や扶養控除を活用できた
筆者も、別居婚で妊娠・出産を経験した際に医療費控除を活用しました。
また、扶養控除についても「住所は別だが、夫が実費を負担していた」ことで対象になり得ると案内された経験があります。
こうした体験をもとに、次章からは控除・給付の制度ごとに具体的な内容と条件を紹介していきます。
【控除編】別居婚でも活用できる減税制度
ここからは、別居婚でも活用できる控除制度を紹介します。
控除をうまく使えば、年末調整や確定申告での負担を軽減できます。
「別居=控除対象外」と思い込まず、それぞれの制度の条件を確認しておきましょう。
医療費控除|別居でも合算できるケース
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引ける制度です。
別居婚でも、配偶者が支払った医療費を合算して申告することができます。
国税庁の公式サイトでは、以下のように説明されています:
「生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も、本人の医療費と合わせて控除の対象となります。」
つまり、住民票が別でも、生活費の負担や共有があれば対象になる可能性があるということです。
私たちも別居中に妊娠・出産があり、帝王切開などで高額な医療費が発生しました。
その際、夫が支払った費用を含めて医療費控除を申告し、還付を受けられました。
👉 詳しくは体験談で紹介しています:
妊娠・出産にかかった費用(別居・別財布夫婦の体験)
注意点:医療費控除は確定申告が必要です。領収書や支払証明書、医療費通知を保管しておきましょう。
参考:国税庁|医療費控除
扶養控除|仕送りで対象になる条件とは?
扶養控除は、配偶者以外の親族(子・親など)を扶養している場合に受けられる所得控除です。
配偶者に対する適用はありませんが、「別居中の子ども」や「遠方の親に仕送りしている場合」などで関係してくることがあります。
また、配偶者との別居状態でも、子どもを主に養育している側が子の扶養控除を申告するケースもあります。
ただし、児童手当との整合性や住民票の世帯構成などが関係するため、申告前に市区町村や税務署へ確認することが大切です。
配偶者控除・配偶者特別控除|住民票が別でも対象?
住民票が別の配偶者でも、「生計を一にしている」ことが確認できれば控除対象となります。
国税庁の説明では、以下のように明記されています:
「住民票の記載に関係なく、実際に生活費や療養費などを共有していれば『生計を一にする』と判断される場合があります。」
実際にわが家でも、夫が私の医療費を負担したことや、子どもの日用品を共有費で支出していたことから、
配偶者特別控除の対象になるかを税務署で確認した経験があります。
共働きや夫婦別財布の場合でも、生活費を一部共有していれば対象になる可能性はあります。
迷ったら、証拠書類を用意のうえで税務署に相談するのがおすすめです。
参考:国税庁|配偶者特別控除
年末調整・申告の注意点
別居婚では、「控除対象配偶者」や「扶養親族」の申告漏れ・誤解が起きやすくなります。
- 年末調整書類で「別居=扶養不可」と判断されがち
- 共働き家庭では、どちらが控除を取るか話し合いが必要
- 医療費控除や出産費用は、確定申告で対応する
会社の年末調整ではカバーできないケースもあるため、確定申告の準備は早めに。
特に別居婚は説明・証明が必要なこともあるため、日頃からお金の流れを記録しておくことが大切です。
👉 関連記事:
夫婦別財布で喧嘩しないためのルール
【給付編】別居婚でも受け取れる手当・補助
次は、別居婚でも受け取れる給付制度・手当について解説します。
出産・育児・通勤など、暮らしに直結する給付を正しく申請することで、経済的な不安を減らすことができます。
ここでも「別居だから無理」とあきらめずに、制度の仕組みと申請ポイントを押さえておきましょう。
出産育児一時金|どちらの健康保険で申請する?
出産育児一時金は、健康保険に加入している人が出産した際に支給される制度で、2024年度からは原則50万円(産科医療補償制度あり)となっています。
別居婚でも、出産した本人か配偶者が被保険者であれば申請可能。
住民票の所在地が異なっていても、保険の扶養関係や加入状況によって、支給されます。
申請先は、本人が加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保など)や、出産した医療機関を通じた「直接支払制度」があります。
わが家では私が社会保険に加入していたため、自分で協会けんぽに申請しました。
なお、高額療養費や医療費控除と併用することで実質負担を抑えることも可能です。
詳しくは:
厚生労働省|出産育児一時金
👉 関連体験談:
妊娠・出産にかかった費用(別居・別財布夫婦の体験)
児童手当|実際に子どもを育てている側が原則
児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育している保護者に支給される手当です(子ども1人あたり月1万円~1万5000円)。
別居婚でも、実際に子どもと同居し、主に養育している側が「受給者」として申請可能です。
ただし、自治体によっては、夫婦それぞれの収入を比較して「所得が高い方」に自動的に指定されるケースもあるため、事前に確認が必要です。
私の場合、子どもと同居している私が受給者として申請し、自治体には別居の実態を説明したうえで、「児童の監護者であること」を確認されました。
東京都独自の制度「018サポート」では独自の月額5,000円給付金もあります。
これは東京都在住の0歳~18歳の子どもを対象に、所得制限なしで支給されます。
「赤ちゃんファースト」制度では、妊娠と出産のタイミングでギフトポイントが支給されます。支給額は最大10万円相当です。
私自身もこれらの給付金やポイントは、別居婚という状況でも、子どもと暮らしている私の家に直接支給されました。
子どもの生活実態に基づいた申請がポイントです。
詳細情報:
こども家庭庁|児童手当 制度のご案内、
東京都018サポート 給付制度、
東京都 出産・子育て応援ギフト(赤ちゃんファースト)
👉 関連記事:
仕事決まったのに保育園に落ちた…別居婚家庭が点数で不利になる理由とは?
育児休業給付金|別居でも取得できる?
育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が育休を取得した場合に支給される制度です。
支給額は原則として、育休開始から180日間は67%、それ以降は50%となっています。
別居婚でも、子どもと同居する親は通常どおり申請できます。
また、離れて暮らすパートナーも、勤務状況や育児実績によっては申請可能です。
ただし、申請の際に育児の実態や同居状況を確認されることがあります。
夫婦それぞれが給付を受ける場合は、育児分担の証明が必要になることも。
わが家の場合、私が子どもと同居して育児休業を取得しました。
給付金もスムーズに支給されました。
重要なのは「どちらが実際に育児しているか」です。
不利になることはありませんが、職場によって申請の手続きが異なるため、早めに確認しておくと安心です。
詳しくはこちら:
厚生労働省|育児休業給付金
👉 関連記事:
0歳の子育てがしんどい…ワンオペで悩んだ私のリアルと今すぐできる対策
会社の住宅手当・通勤手当|住所が別でもOK?
勤務先によっては、住宅手当や通勤手当が別居婚にもしっかり適用されます。
住宅手当については、「世帯主であること」「会社に届出をしていること」が要件になっているケースが多いです。
配偶者と別居していても、自分の住まいにかかる家賃補助として受け取ることができます。
一方、通勤手当は実際の通勤経路と交通費に基づいて支給されるため、別居婚でも問題ありません。
たとえば、週末に配偶者の元へ移動している場合でも、通勤手当は日常の勤務先への交通費として支払われます。
ただし、住所変更や通勤経路の申告漏れがあると、トラブルの原因になることも。
人事部門に早めに申請・確認しておくのが安心です。
会社によっては「別居=単身赴任扱い」として、家賃補助や転居費用などの手当が追加されることもあります。
別居婚だからといって損をするとは限りません。
制度だけでなく、勤務先のルールも活用できるか確認しましょう。
よくある疑問と別居婚ならではの注意点

ここでは、制度を使う前によく出てくる疑問や、別居婚ならではの落とし穴をまとめました。
申請で損をしないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
世帯分離すると損?得?
別居婚では、住民票を分けて世帯分離している家庭も多くあります。
世帯分離をすると、それぞれが独立した世帯として扱われます。
そのため、住民税や国民健康保険、年金などの金額に影響が出ることがあります。
控除や手当の扱いも変わる場合があるため、事前に役所や税務署で確認しておくのが安心です。
共働きの場合、誰がどの制度を申請する?
共働きの別居婚では、どちらが控除や給付を受けるのかを話し合っておくと安心です。
たとえば児童手当は、子どもと同居している側が受給者になります。
扶養控除は、所得の低いほうが申請することで節税効果が高くなるケースが多いです。
「別居婚だと不利」と言われる理由と実際
保育園の申請などでは、「夫婦で協力しにくい」と評価される場合があり、点数に影響することもあります。
一方で、控除や給付金の制度は、条件を満たせば別居でも利用可能です。
書類や説明がやや複雑になることもありますが、事前に相談しておけば柔軟に対応してもらえることも多いです。
👉 関連記事:
仕事決まったのに保育園に落ちた…別居婚家庭が点数で不利になる理由とは?
申請前に確認すべき3つのポイント
- 住民票の所在地(同一世帯か別世帯かで制度の扱いが異なる)
- 生活実態(育児や生活費の分担など)
- 自治体や会社のルール(支給条件や必要書類が違うことも)
この3つを押さえておくと、制度申請がスムーズになり、損を防げます。
別居婚でも制度を使って安心できる暮らしを
別居婚だからといって、控除や給付の制度をあきらめる必要はありません。
条件や生活実態が整っていれば、同居家庭と同じように制度を活用できます。
この記事で紹介した内容をふまえ、申請前には以下のポイントをチェックしてみてください。
✅ 別居婚でも使える制度があることを知っておく
✅ 控除・給付ごとの条件や手続きを確認する
✅ 住民票や生活費の実態を証明できるように準備する
✅ 自治体や勤務先にも早めに相談しておく
別居婚には「説明が少し面倒」「書類が増える」などのハードルもあります。
でも、制度を正しく使えば、安心感のある二拠点生活が現実的になります。
大切なのは「知らずに損をしないこと」。
ぜひ活用できる制度を見つけて、あなたらしい暮らしを守っていってください。