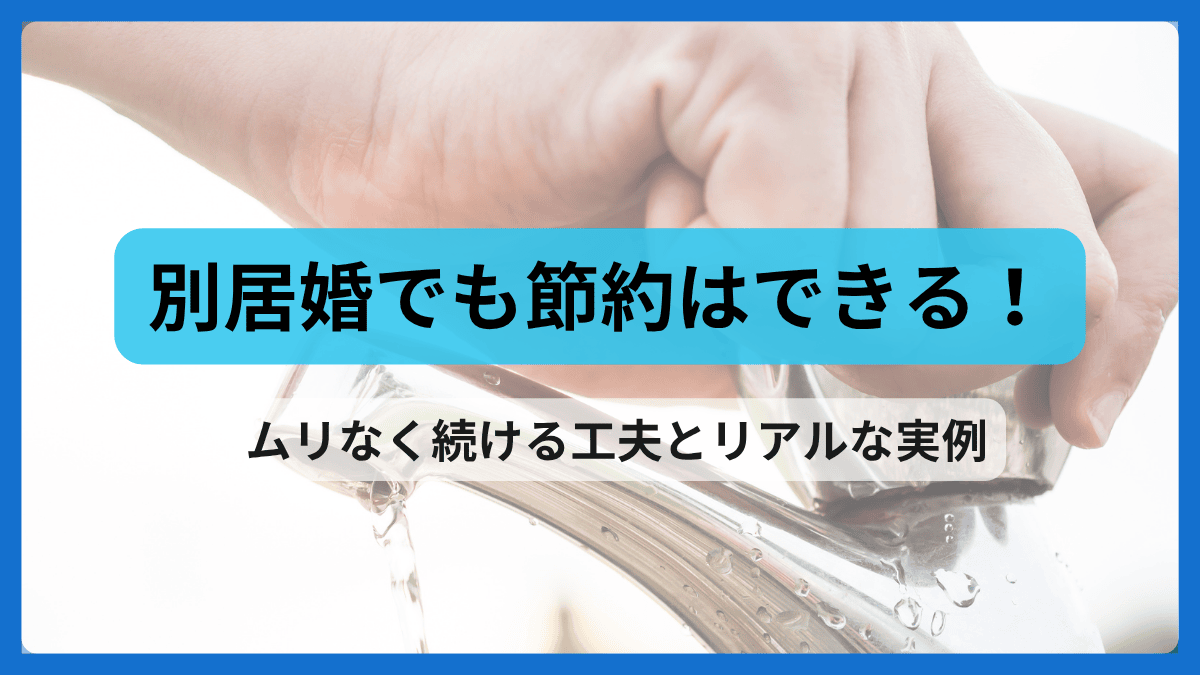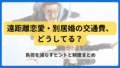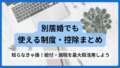別居婚でも節約はできる?二拠点生活の工夫とリアルな節約術8選
「別居婚って、やっぱりお金がかかるよね?」
結婚しても一緒に住まず、互いに自立した生活を送る——そんな“別居婚”は、ライフスタイルとして注目される一方で、「生活費が2倍になるのでは」と不安を感じる人も少なくありません。
確かに、家賃・光熱費・交通費など、二拠点生活には独特のコストがかかります。
でも、実際に別居婚をしている筆者は、無理せず“自分たちらしいやり方”で節約を続けながら、心地よく暮らしています。
この記事では、そんな筆者の実体験をもとに、別居婚でも続けやすい節約アイデアと考え方を紹介します。
「節約=ガマン」ではなく、「賢く選ぶ」「夫婦で工夫する」視点をお届けします。
🔍 この記事でわかること
- 別居婚が「お金がかかる」と言われる理由
- 実際にやっている節約術とその効果
- 制度やツールを活用した支出の抑え方
- 無理なく続けるための考え方と習慣
別居婚でお金がかかるのはなぜ?二拠点生活の特徴と出費

「別居婚=生活費が2倍になる」と言われるのはなぜでしょうか。
実際に暮らしてみると、同居と比較して増える出費には共通点があります。
このパートでは、私たち夫婦の実体験をもとに、二拠点生活でかかる主な費用とその理由を3つに分けて紹介します。
一人暮らしが2つあるようなもの
別居婚では、夫婦がそれぞれ別の家で暮らすため、住居費・光熱費・食費などがすべて“2人分”必要になります。
まさに「一人暮らしが2つある状態」です。
例えば、夫が東京で家賃9万円、妻は地方で家賃6万円。光熱費や通信費を含めると、毎月の固定費は合計20万円を超えます。
同居であれば半分で済んでいた金額なので、ここは大きな負担ポイントです。
交通費や移動コストも大きい
遠距離別居婚では「会うための交通費」も見逃せません。
新幹線や飛行機、車移動など、月に1〜2回の往復でも数万円の出費になります。
我が家の場合は月2回の新幹線往復で約3万円。年間で約36万円。
▶︎ 遠距離別居婚の交通費まとめでも紹介していますが、割引制度や会社の福利厚生を使わないとかなりの痛手です。
「共同購入」ができずコスパが悪くなる
同居であれば1つで済むものも、別居だと2セット必要になります。
洗剤・調味料・ティッシュなどの日用品から、家電や家具までコスパが悪くなりがちです。
また、サブスクもそれぞれ契約すると割高になります。
別々にAmazon PrimeやNetflixを契約していたことに気づき、「これって無駄かも?」と話し合って見直したこともあります。
こうした“見えづらい重複出費”に気づくことが、節約の第一歩になります。
別居婚でもできる!節約アイデア8選

「生活費が2倍になる」と感じる別居婚でも、工夫次第で出費を抑えることは十分に可能です。
このパートでは、私たちが実際に取り入れて効果を感じた節約アイデアを8つ紹介します。
「我慢」ではなく「仕組み」で無理なく続けられることを重視しています。前半では特に、固定費や通信関連の見直しに焦点をあてます。
格安SIMや家族割で通信費を見直す
別居婚でも、契約プランを見直すだけで毎月の通信費を大幅にカットできます。
私たちは大手キャリアから格安SIMに切り替えたことで、月々1人5,000円以上の節約になりました。
また、同居していなくても「家族割」が適用されるケースもあるため、各キャリアのルールをチェックするのがおすすめです。
▶︎ 価格.comの格安SIM比較ページで料金やサービスの違いを簡単に確認できます。
サブスクは共有または集約する
NetflixやAmazon Primeなどのサブスクリプションサービスは、夫婦で重複契約せずにどちらかにまとめることで節約に。
また、同じアカウントをシェアできる「ファミリープラン」や「同時視聴プラン」も活用するとコスパがアップします。
価値観の違いで「別々に契約したい」場合も、月1で見直す日を決めておくと、話し合いやすくなります。
▶︎ 夫婦別財布でのトラブル回避のコツも参考にしてください。
ふるさと納税で生活必需品をカバー
生活費を抑える手段として有効なのがふるさと納税です。
私たちは、トイレットペーパー・洗剤・お米などの返礼品を選ぶことで、日用品購入の頻度を減らしました。
実質2,000円の自己負担でこれだけの返礼があるのは大きなメリットです。
▶︎ 国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」で、制度の詳細や申請方法を確認できます。
回数券・株主優待・会社補助を活用する
交通費を抑えるなら、各種の割引制度は要チェックです。
特に新幹線や航空券は、回数券や株主優待、会社の福利厚生制度を活用することでかなり安くなります。
私たちは、回数券を購入して、片道あたり1,000円以上の節約になったことも。
▶︎ 遠距離別居婚の交通費まとめで具体例や比較を紹介しています。
家計簿アプリでお互いの支出を“見える化”
別居婚ではお金の流れが把握しづらいため、家計簿アプリで情報を共有するのがおすすめです。
「何にどれだけ使っているか」を可視化することで、節約意識が高まり、話し合いもスムーズになります。
私たちは OsidOri(オシドリ) という夫婦向け家計簿アプリを使用中。
収支の記録だけでなく、買い物リストや今後の支出予定も共有できるので便利です。
電力会社や契約プランを見直す
二拠点生活では電気代が2つの家にかかるため、電力自由化の恩恵を活かすのが節約の鍵。
特に一人暮らし用の省エネプランを選ぶことで、月1,000〜2,000円程度の節約になるケースもあります。
▶︎ エネチェンジ「電気料金プラン比較」を使えば、自宅の電気使用量に合った最安プランを簡単に探せます。
月1の「家計会議」で目標とルールを調整
節約を続けるには、定期的な“振り返りの場”が重要です。
月1回の「家計会議」を設け、先月の支出や今後の出費予定を話し合うだけでも無駄遣いが減ります。
また、「貯金目標を共有する」「お互いに責めない姿勢を取る」など、安心して話せるルールづくりもポイントです。
家計会議をうまく進めるコツは、
▶︎ 夫婦別財布で喧嘩しないためのルールにもまとめています。
「話しやすい空気」をつくる工夫を
節約には、パートナーとの“温度差”が壁になります。
まずは「一緒に見直したいけど、どう思う?」と切り出すことで、対等な話し合いが始まりやすくなります。
また、数字やグラフなどの客観情報をもとに話すと、感情的になりづらく、冷静に話し合えるのでおすすめです。
我が家では、LINEで毎月の家計サマリーを送ってから話し合うようにしています。自然な対話の流れが生まれます。
節約を続けるために大切な考え方
「節約しなきゃ」と思うほど、プレッシャーになって長続きしないものです。
別居婚では、夫婦それぞれの生活にリズムがあるからこそ、「頑張りすぎない」節約が大切です。
支出の「納得度」を重視する
金額の多寡よりも、「自分たちが納得しているか」が大切です。
たとえば、多少コストがかかっても「お互いが会いに行くときは少し良いホテルに泊まりたい」「冷凍食品を買ってでも自炊の負担を減らしたい」など、価値観のすり合わせが節約のカギになります。
「夫婦で節約ルールを育てる」意識を持つ
節約のルールは、最初からうまくいかなくてもOK。
1回やってみて続かなかったら、少し変える。ゆるくても「わが家のやり方」を作っていくことが、ストレスなく続けられる方法です。
共通のゴールがあると意識が揃いやすい
「子どもが生まれるまでに〇万円貯めよう」「次の旅行のために節約しよう」など、目指すものがあると協力しやすくなります。
価値観にズレがあると感じたときは、▶︎ トラブル回避の考え方も参考にしてみてください。
別居婚でも節約はできる|自分たちらしいやりくりで安心を
- 別居婚では生活費が2重になりがちだが、節約術でカバー可能
- 通信費・交通費・サブスクなどは見直しの効果が大きい
- 制度やツールを活用して“続けやすい仕組み”をつくろう
節約は「支出を減らすこと」よりも、「自分たちに合ったルールをつくること」が大切です。
我慢ではなく、納得して続けられる方法を夫婦で見つけていきましょう。
▶︎ 関連記事